オンラインキャンパス
こまどりキャンパス



2月13日(金)遠足でえひめこどもの城に行きました。午前中は、木工体験の、キャビネットづくりをしました。こどもの城のスタッフの方の助けを借りながら、糸のこを上手に使い、思い思いの作品を作りました。午後からは、てんとう虫のモノレールやボブスレーなどの乗り物に乗ったり、公園で鬼ごっこをしたりして楽しみました。子どもたちの笑顔があふれ、心に残る1日となりました。
オンラインキャンパス
こまどりキャンパス



1月30日(金曜日)イベントタイムに愛媛県生涯学習センターのグラウンドをお借りして、たこ揚げを行いました。
各自が好きな絵を描いて、個性溢れるたこを作りました。また、書初めの作品「馬2026」を貼り付けた、こまどりキャンパス特製のたこも作りました。快晴の中、それぞれがグランドを駆け回り、見事にたこが揚がりました。寒さに負けず、笑顔で楽しめた1日でした。
こまどりキャンパス
1月23日(金曜日)、昭和女子大学の森先生を講師に迎え、第3回こまどりキャンパスワークショップを行いました。
今回は、専用アプリを活用した絵本づくり活動です。ストーリーを考え、キャラクターの配置や体の動き、背景などを細かく決めていきます。みんな集中して取り組み、あっという間の90分でした。最後にプリントアウトして小さな絵本の完成です。
今年度のワークショップは、今回で終了です。来年度も、森先生と一緒に楽しい活動を計画していきます。楽しみにしていてくださいね。



オンラインキャンパス
こまどりキャンパス
こまどりキャンパス



12月24日(水曜日)クリスマス会と2学期の終級式を行いました。
クリスマス会は、チーム対抗宝探しゲームやビンゴゲーム等で盛り上がりました。終級式では、写真を見て2学期を振り返り、楽しかった思い出について話しました。2学期のこまどりキャンパスも、笑顔いっぱいで終えることができました。
冬休み中は、午前中に一部開級しており、セレクトタイム、ソーシャルタイム、ラーニングタイムのどれかを選んで、自主活動を行います。開級日については、ホームページの月行事予定をご覧ください。
保護者学級
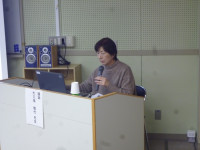


12月24日(水)第5回保護者学級を行いました。今回は、大久保雅代先生を講師としてお招きし、「学校に行きづらい子どもとの関わり方」という演題で講演会を行いました。親自身の不安や辛さに共感していただきながら、再登校を目指した対応や、長期的視点に立って、回復のために大切なポイントを教えていただきました。参加された方からは、「子どもの思っていることや親の対応の仕方など、具体的に教えてもらい、勉強になった。」「親として、焦らず自然体で子どもとうまく関わっていきたい。」「今の自分に共感できる言葉をたくさんもらい、今日の講演の話を基に子どもとうまく関わっていきたい。」という感想がありました。
オンラインキャンパス
オンラインキャンパス
こまどりキャンパス



11月28日(金曜日)イベントタイムで、スイートポテト作りを行いました。こまどりキャンパスの畑で育てたサツマイモを、茹でてつぶし、バターや砂糖、牛乳を混ぜました。みんなで楽しみながら、協力して調理することができました。最後に食べやすい形に整え、トースターでこんがり焼いて完成。甘くてホクホクのスイートポテトが出来上がり、秋の味覚を堪能しました。
オンラインキャンパス
こまどりキャンパス



11月12日(水曜日)県内の教育支援センター又は教育支援教室に通う児童生徒同士が、親睦を図ることを目的とした「こまどり交流会」をオンラインで行いました。教室紹介クイズでは、4択形式で出題し、普段の活動の様子を互いに説明し合いました。ジェスチャーゲームでは、身振り手振りを上手に使って表現できました。ランキングビンゴでは、好きなおにぎりの具材を予想しビンゴを目指しました。たくさんの笑顔が見られた素敵な時間を過ごすことができました。
オンラインキャンパス